
冬休みはゲーム三昧。冬休み明けはどうなるんだろう
ブログをお読みいただきありがとうございます。MIKURU・MIRUのまいどん先生こと山下です。
本年もスタンドエフエムの最初の挨拶配信でお話したように、お母さんがひとりで悩みを抱えて精神的に追い詰められて悲しい出来事が起きてしまう…ということが少しでも減っていってほしいという願いを込め、子育てに悩まれている親御さんに寄り添い、支援をいたします。
これからも、様々なカタチで情報発信も続けていきますので、応援していただけると大変はげみになります。
みなさま本年もよろしくお願いします(*^^*)
楽しい冬休み!あなたのお子さんはゲームをしますか
楽しい楽しい冬休み。
クリスマスにサンタさんがやってきたり、お正月はお年玉をゲットできたり。
冬休みを心待ちにし、この2つのイベントにワクワクし、「早くサンタさんからのプレゼントで遊びたい!」「お年玉でこれを買おうかな」「お年玉で課金するぞ~」など12月に入ってすぐに計画を立てていたお子さんは多かったと思います。(話はそれますが子どもの頃、私のもとにはサンタさんがこなかったのでクリスマスが嫌いでした 😥 )
長かった2学期が終わり、クリスマスにサンタさんからSwitchやソフトをもらって、操作に慣れない中色々工夫したり調べたりしてゲームに没頭したり、もともとハマっていたスプラトゥーンやフォートナイトやエイペックスなどに集中したり…と、この冬休みにゲームスキルが上達したお子さんは多いのではないでしょうか。
今は昔とちがい、友達と遊ぼうと思ったらお友達の家まで行ってピンポンを押したり、お友達のお家に電話をかけて「〇〇くんいますか」と変わってもらうことをしなくても、親御さん同士がつながっていればLINEで遊べないか確認してもらえたり、ゲームを起動したらオンラインで友達がゲームをプレイしているのがわかるのでそれに加わることができたりと、ひと手間かけなくてもすぐにやりとりができる時代です。
ゲームを一緒にしようと思えば友達に家に来てもらうか行くかして一緒にテレビの前に並んでゲームをしなければならなかったのが、それぞれが家にいながらオンラインでつながってプレイできたり、ボイスチャットを楽しみながらプレイできたり、LINE通話をしながらプレイできたり…と便利な時代になりました。
だからこそ「友達にゲームに誘われて断れない」「友達と約束していた時間にプレイするということを最優先にタイムスケジュールを組まなければならない」「下手だからときつい言われ方をされる」「うまく遊べなくてイライラする」という悩みもうまれやすいです。
私は普段からゲームをする人なのでそれ自体は悪いものではないと思っていますし、ゲームから学べるものは多いと思っているので、ゲームはしないほうがいいとは思っていない人間です。
また、様々なご相談を受けていると、ゲームをしない少数派のお子さんはクラスの子たちと話が合わない苦労をしていることも多く、コミュニケーションツールのひとつとしてある程度はゲームを知っていたり、できないと大変だとも思っています。
「足が速い子は男女ともにモテる」のと同じように、「ゲームがうまい子は男女ともにモテる」のは小中学生あるあるでもあるので、
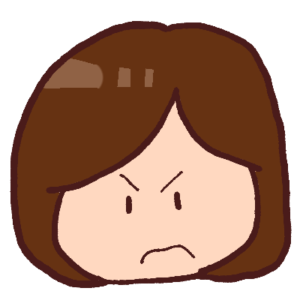
と怒らずに、


という視点を持つことも大切だと考えます。
生活リズムの乱れやルールを守ることができないから行きしぶりが起きる?
しかし、多くの親御さんは



ということを悩まれているのではないでしょうか。
せっかくゲームのルールを設けたのに守らなかったり、ゲームが原因で親子で揉めたり、ゲームが原因で生活リズムが乱れたり、子どもが外にでなくなったり。
「こんなことになるならばゲームを買うんじゃなかった」
とすら思われている方は少なくないのではないかと思います。
たしかにMIKURU・MIRUのもとにご相談をいただきうケースの中には、ゲームに夢中になりすぎて生活リズムが乱れ、新学期がスタートしたにもかかわらず生活がもとにもどらなくて学校にいかなくなったというご相談をいただくことは少なくありません。
「ゲームにハマった」はきっかけでしかない
しかし、よくよく話を聞いてみますと、たしかにゲームを買ってもらったりハマったことがきっかけで行きしぶりや不登校になったものの、それが根本的な原因となっていたかというとそうでないことがほとんどです。
例えば…
・部活で思うように活躍できないという悩みが以前からあった
・友達関係に悩んでいた
・定期テストで思うような点数が取れなくて落ち込んでいた
・通学でかなり疲れていた
・親子でゆっくり話すことがなく、子どもは家での発言が減っていた
・母子あるいは父子の関係があまりよくなかった
…など、ゲームにハマる以前から子どもの様子がいつもと違っていた…ということが多いです。
「思い過ごしかなと思って気にしないように親はしていた。子どももなんだか表情は暗いままだったけれど学校には行っていたから気にしないようにしていた。ゲームを買ってあげて冬休みにのんびりするとリフレッシュもできるだろうし、また新学期からがんばるだろう。」
…そう考えていたけれど、冬休み明けから「行きたくない」「お腹いたい」「…(起きない)」となってしまう。
そこで親がゲームを取り上げようとしたら大暴れして壁に穴が空いたとか、母親は思いっきり殴られて骨が折れた…ということもあります。
これは子どもがもともと何かに悩んでいたり「学校に行きたくない」と苦しんでいる時に、目の前にゲームというハマれるものがあらわれたことで、現実逃避がしやすい環境になっただけであって、ゲームがあるから学校にいかなくなったというわけではありません。
「ゲーム=悪」
というわけではなく、そもそも学校に行きたくなくなった理由は何なのか。子どもが悩みを抱え込んで解決できないままだったのはなぜなのか。親は子どもに寄り添い話を聞いてあげられていたのか。知らず知らずのうちに周りが子どもにプレッシャーをかけて「過剰適応」させてきていなかったか。
まずはそういった点に着目して考えていく必要があると私は考えます。
まとめ
今回は、ゲームと行きしぶりについて記事を書かせていただきました。
支援をしていますと本当に色々なケースとの出会いがあります。ゲームが学校生活を豊かにしてくれたケースもあれば、ゲームがあるからこそいじめに悩むケースもあります。
親子で楽しくプレイして親子の関係性がよくなるケースもあれば、ゲームが原因で親子喧嘩ばかりになるケースもあります。
スマホでもネットでもなんでもそうですが、便利なものはうまく活用すれば生活をメリハリある豊かなものにしてくれます。
しかし与える前段階できっちりルールやペナルティの話し合いができていなかったり、「冬休みだからいいか」と甘くしすぎたり、ギチギチのルールでしばったりするとかえって揉める種になりかねません。
「じゃあうちではどうすれば?」と思われる方も多いとは思いますが、ブログにて「こうです」とはなかなかいえません。
なぜなら、ご家庭によって状況は様々で、たとえ8割のご家庭に合うやりかたであっても、2割のご家庭にとってはむしろ状況を悪化させてしまう可能性があるからです。
(支援の場ではご家庭をしっかり分析させていただいた上でアドバイスを差し上げています)
ただ、少なくともゲームを与えるからには、
・親が子ども以上にゲームの取り扱いについて調べて知っておくこと
・ルールを細かくしすぎないこと(宿題やお手伝いやテストの点数などゲームにまつわるルールを広範囲にしすぎない)
・ルールを徹底する姿勢を親は見せ続けること
といったところは最低限意識すべきところかなと思います。
その上で、子どもたちにはせっかく手に入れたゲームで楽しく遊びリフレッシュしたり、友達との仲をより深めていくツールのひとつとしてうまく活用していってほしいものですね。
それでは、今回はこのへんで終わりたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
親まなびアドバイザー まいどん先生
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇月に1、2回 家庭教育に関する情報発信中!:公式LINEはこちら