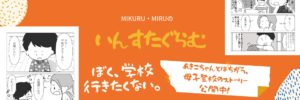アイメッセージでやりとり…実は逆効果な場合もある?後編
ブログをお読みいただきありがとうございます!前回からの続きです。
鏡神経ミラーニューロン
そもそもどうして子どもが親の気持ちを読み取れるのか?ですが、
人間には、人間同士が語らなくても同じ気持ちになれる能力があり、これを『共感』とよびます。
互いに反応し合う神経細胞をミラーニューロン(鏡神経)といい、これがあるからこそ人間は相手への理解がしやすくなるといわれています。
目の前でこけたひとをみてうわっと顔をくしゃっとしたり(痛みの共感)、目の前の人があくびをしたら自分もあくびをしてしまう(眠気の共感)というように、相手の行動を見て、鏡に写すように自分の脳内で真似て同じ感情を呼び起こす反応をします。
もしもアイメッセージで「お母さんは早くお風呂に入りたいなぁ…」と伝えていても、
心の中では「はよ入れや 👿 イライラするな!ったく毎日毎日だらしない!!!私が普段どれだけあなたに譲ってきてるかわからないの!!!」と思っていたら、子どもは親の言葉と雰囲気などの矛盾に気づき、やたら親の顔色をうかがうか、反発が返ってきやすいです。
「えらいね。」「うれしいわ」「助かるわ」などと褒めながら、「それくらいやって当然やろ」と実は子どもを見下していた。
言うことを聞かせようと思って、何度もアイメッセージで伝え、行動変容を促そうとした。
子どもが失敗することが恥ずかしくて、誘導しようとした。
寄り添ったつもりの行動には親の理想や都合が隠されていることを子どもは読み取っていた。
アイメッセージをつかい子どもの自主性や自立心をはぐくむという名目で、子どもが親の言うことを素直に聞くという支配関係を期待していた。
そういうことを、子どもが実は読み取っていて、一生懸命アイメッセージを使おうとしてもうまくいかないどころかどんどん関係性が悪くなる…というケースをよくみかけます。
本音を隠さない
そこで私がカウンセリングを受けてくださっている親御さんには、よく

…と言っています。

みたいなこともよく言います。
すると、「先生の仰った内容、まんま私の本心です…そんなことを毎日思い、でもそんなことを言ってはいけないと思って、飲み込んで、我慢しています…」と返ってくることがほとんどなのですが、私は、『まずはその本音をちゃんとどこかで吐き出しましょう』と話します。
キレイなことを言おうとするのはいいけれど、本当は心の中では思うことがある。でもそれを表に出してはいけないと思って言いたいことを飲み込む。
心ではドロドロがどんどん深くなり、腐敗していく。本音を隠そうとして、表面的なやりとりで演技がかってくる。
お母さんの表情がどんどん読めなくなって、子どもはそんなお母さんをきもちわるいとか、怖いと感じてしまうこともあります。
「言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズン」は実は(?)めっちゃ大事なこと言うてるなと思うんですね。
ちゃんと本音を吐き出して、まずはお母さんが現状にどう感じているのかをちゃんと見つめないと、ただただ「毎日子どものために自我を殺して演技をして耐える日々」に対する疲労が蓄積され、自分の気持ちがわからなくなり、原因不明のイライラに悩まされることになります。
「夕飯の時にお箸を出してくれって何回言わせるねん。仕事も家事もしてヘトヘトやのに、ご飯を作ってもらって当たり前。必要なものは親に出してもらって当たり前。片付けも親がやって当たり前。…みたいな態度、腹立つ!」
という本音をちゃんと見つめたら、それをどうアイメッセージで伝えればいいのか?ということを考えることが大事だと思うんです。
「ご飯の時にお箸を出してくれたらうれしいな」よりも、
「お母さん、これまで何度も夕飯の時にお箸を出してくれって言ってきてたでしょ。あなたも学校に通って帰ってきてくたくたなのはわかるよ。でもね。実はお母さんも毎日仕事と家事でヘトヘトでね。ご飯を作ってさあ食べようねという時に、だれにも手伝ってもらえないと自分がお手伝いさんみたいに感じて悲しい気持ちになるのよ。」
のほうが、子どもにストレートに伝わる可能性がありますし、具体的に親の気持ちを伝えられているし、親自身も自分の気持ちを無視せず、ちゃんと大事にできています。
自分は今どういうことに不快なのか。喜びを感じているのか。ということを具体的に言えたほうが、お互いに分かり合えますし、子どもがこういうふうに自分の気持ちを言えるようになった方が、親は子どものことを理解しやすいですよね。
まとめ
アイメッセージは、多くの書籍やブログで取り扱われているテーマです。
今回書かせていただいたのは、あくまでも『私が思うアイメッセージ』の在り方なので、これが正解ですとはいえませんが、カウンセリングを受けていただいている親御さんがたには耳にタコができるほど「矛盾があるやりとりを控えましょう」「お母さんの本音は?」「本当はどう思っていますか」「うそをつくくらいなら言わないほうがいいです」と伝えてきています。
小学生にもなれば、子どもは大人の微妙な雰囲気に気づきます。
親の言葉と雰囲気の矛盾がわかってしまいます。
本音を押し殺したコミュニケーションが当たり前になると、子どももまた本音を押し殺すコミュニケーションが当たり前になっていきやすいとも考えられます。
テクニックだけに頼らず、親子会話をよりよくしていくための手法のひとつくらいにとらえて、日々のやりとりをよいものにしてみていただければ嬉しいです。
それでは、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。最後までお読みいただきありがとうございます。
次回のブログもお読みいただけたら嬉しいです 🙂
まいどん先生(公認心理師)
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇Instagramはこちら