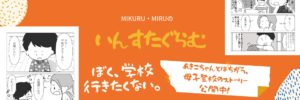『分離不安』と診断される場合何が基準になるのか・前編
ブログをお読みいただきありがとうございます。MIKURU・MIRU代表 公認心理師のまいどん先生です。
今回は「不安症」をテーマに2回にわけて記事を書いてみたいと思います。
母子登校と不安症
今年で支援者として12年活動をしてまいりましたが、肌感覚的に不登校よりも母子登校中のお子さんのほうが不安の訴えが多いように思います。
これは、不登校のほうが外に出たり、他者との接触がすくないため、不安を感じるきっかけや刺激を受けにくいからではないかというのが個人的意見です。
高学年よりも低学年のお子さんのほうが不登校初期は不安の訴えが強く、欠席日数が長くなるにつれて不安の訴えがマシになることもありますが、マシになったり酷くなったりを繰り返すケースもお見受けします。
不安症といいますと、
・何に対してもいつも不安で仕方がない状態が続く「全般不安症」
・動物(虫や犬等)自然環境(雷、水等)状況(嘔吐、閉所等)といった特定のものに強い恐怖感を抱く「○○恐怖症」
・ある一定の状況になるといつも喋れなくなる「選択的緘黙」
などが見られます。
・何に対してもいつも不安で仕方がない状態が続く「全般不安症」



…と、いうようなケースはこの状態に近いといえるかもしれません。
ただ、これらは実は以下のようなことが関係していることも。
・『学校を休めば休むほど、不安が膨らんでいるようにみえます』
→学校を休む期間が長くなればなるほど、母子登校が長くなればなるほど『周りからどう見られているんだろう』『周りと自分の差に落ち込んでしまう』というお子さんもいます。
また、例えば学校では毎日50程度の刺激を受けて帰ってくるのでそれくらいの刺激には対応できるけれども、学校に行かなくなることで刺激を受ける量が減って(他者との関わりが少なくなる等)毎日10程度の刺激の中で過ごすのが当たり前になることがあります。
そうすると、学校に行っている時は30くらいの刺激が突然やってきても驚かないのに、言っていない時は毎日10程度の刺激の中で生活をしているので、その差に驚いてびくびくしてしまう。不安になってしまう…ということもあります。
・『鍵は閉めた?2階に行くのが怖い。風の音が怖い。…など、あらゆることに怖い、不安というようになりました』
→こちらも上の理屈と同じで、多少の刺激にも過敏になってしまったり、些細なことが気になることが増えてしまってこのような状態に陥っていることがあります。
また、何かしんぱいごとがあると、他のことまでつられて気になってしまうということも。(扁桃体が過活動状態)
・『ゲームで失敗したらどうしよう。料理でうまく卵が焼けなかったどうしよう。など、失敗してもどうってことないことに対しても不安を訴えます』
→こちらも上の理屈と同様です。
また、割と多いのが、親子会話が原因になっているパターンもあります。
(例1)




(例2)







どのご家庭にでも見られるようなやりとりだと思われたと思うのですが、よくよく読んでみると、例1も例2も、お子さんは『こうなったらどうしよう』『これがやってみたい』とは言うものの、「どうしたらいいかアドバイスが欲しい」とは言っていません。
親御さんがお子さんとのやりとりにおいて、これまでの会話パターンから『あ、これは解決策を求めてるな』『また不安になってるな』と先読みをして「こうしたら?」とアドバイスをしてしまうということをよくお見掛けします。
しかし、もしかしたら子どもはアドバイスを求めているのではなく、ただ話を聴いてもらいたかっただけだったり、自分の気持ちを言葉にしたかっただけなのに、親が「こうしたら」とアドバイスをいれたことで自分の予定になかったアドバイスをされて混乱してしまっているだけ…ということもあり得ます。
👇詳しくは過去のブログでも解説していますので、よければお読みください
・動物(虫や犬等)自然環境(雷、水等)状況(嘔吐、閉所等)といった特定のものに強い恐怖感を抱く「○○恐怖症」


こんなふうに何か特定のものに強い恐怖をいだく場合は、虫恐怖症や嘔吐恐怖症に当てはまる場合も。
動機・冷や汗・過呼吸…など、パニック状態になってしまう場合はこれらを疑うことがあります。
・ある一定の状況になるといつも喋れなくなる「選択的緘黙」

不登校や母子登校のご相談では結構多いのがこちらです。
実は検査を受けてみると発達障害(ASD)のケースだった…ということもあれば、普段からお子さんが何かを答えるべき場面でお母さんがお子さんの代わりに答えてしまうようなことが当たり前になっていることから、学校においてもお母さんに連れられて学校に行った時に、担任の先生からの質問に自分で答えようとせず、お母さん任せにしてしまうことが原因だった…というケースもあります。
(例)







…と、このように、先生からの問いかけにお母さんが代わりに答えることが当たり前になっていると、お子さんはお母さんにアウトソーシングしたい気持ちが強くなり、黙ってお母さんをチラチラ見てしまう。お母さんは、先生に申し訳ないと思って子どもの代わりに受け答えをしてしまう…ということがあります。
こういったケースは普段から、お父さんがお子さんに話しかけているのにお母さんがお子さんの代わりに答えてしまう…というようなやりとりが日常化していることもあり、親子会話を変えていくことで先生とのやりとりも自分で出来るようになったということもあります。
このような後者の場合は、選択的緘黙というより、自立面で課題があったということになります。
長くなったので、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。最後までお読みいただきありがとうございます。
また次回のブログにてお会いしましょう 🙂
まいどん先生(公認心理師)
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇Instagramはこちら