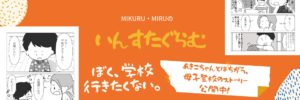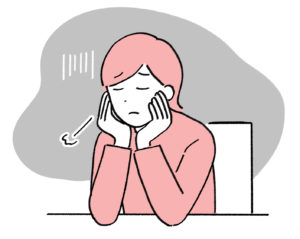
小さい頃に親から認めてもらえなかった子どもは大人になっても自分を認めることができない・後編
まいどん先生です。前回の続きです。
子育て、親子の関わり、家庭教育をまなんでいくと…
たとえば「ママ、ぼくもう今日宿題しないから」と言われたとき、「またそうやって私を試す!わがまま言う!」と怒りに包まれていたけれども、支援を受けることで親子の関わりを客観視していくと、

ということがわかったりします。
よく、『子どもが宿題を嫌がったときの対応法5選』みたいな情報がネットには転がっていますが、必ずしもどの家庭に当てはまるとは限りません。
どのお子さんも必ず毎回同じ条件で宿題を嫌がるというわけではないですし、なぜ宿題を嫌がったのかというのもそれぞれです。
そのような状況で、「なんちゃら対応法」みたいなのをやってもかみ合わないことがあります。
やってもやっても手応えを感じられないと、「なんだ、所詮はこんなもんか」と早い段階で見切りをつけてしまいたくなりますよね。
カウンセリングを受けてみると、「子どもの言葉を勝手に解釈して受け取っていただけだったんだ」と気づく。
そして、子どものみる世界や考える頭の中を、できる限り親側の主観をまじえず理解しようとする聴き方を知ると、子どもをより理解できるようになっていきます。

…と気づけるようになっていきます。
聴き方の訓練をコツコツ積み重ねていくと…
聴き方の訓練をコツコツ積み重ねていくと、お母さんがカッとなったときに出そうな言葉がおさえられるようになっていきます。
これまではコンマ1秒で、
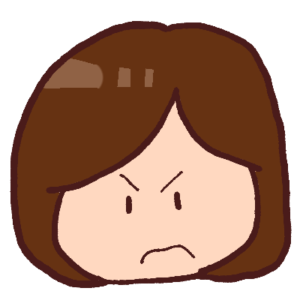
…と子どもを押さえつけるような言い方しか出来なかったのが、子どもの視点も持てるようになると、

…とも思えるようになり、爆発からの自己嫌悪も減っていきます。
そして、カウンセリングの中では、自分のモヤモヤを整理してもらったり、言語化されてスッと消えていく。


…と嬉しくなったり。
そして、カウンセリング後にこれまで我慢していたことを思い出して涙を流すこともあるかもしれません。
心に溜まってしまったものが、浄化されていくように、
そして、孤独から脱し、コツコツ親子の関わりを変えていくと、自分で納得のいく関わりも見つかっていきます。
これまでずっと手探りで、答えのない中、孤独に子育てをしてきていたけれど、「こうやって対応をすればいいんだ。関わればいいんだ」とわかると、うれしくなるものです。
そうすれば、しんどい朝も、追いつめられることなく、「そういうこともあるよね。そういう日もあるよね。これも子育ての1ページだわ…」
と思えるようになっていくはずです。
振り返ればきっとあっと言う間の、自分の苦悩も全部ひっくるめて、愛おしく思える毎日をかみしめ、怒って泣いて笑って悲しい、そんな毎日の親子のやりとりを大切にしてほしい。
私はそのような願いをこめて、皆さんのお話をうかがっています。
子どもを認めていこう
これは、「100点とれたわね。偉いわ」「友達がたくさんいてすごいわね」というような、表面的で結果にだけ注目するような『認める』とはまた違います。
『どんな自分であっても肯定してくれた。どんな自分の感情をも受け止めて理解しようとし続けてくれた』この感覚を持ってもらえるような関わりが『認める』です。
みなさんは、ご自身の親と『感情の共有』をした経験はありますか。
自分が夏休みの宿題の習字で金賞を取ったとか、50m走で一位を取ったとか、授業での取り組みで先生にほめられたとか、結果に対して喜ばれたというのとは違います。
| うまく表現ができない自分の心のモヤモヤにそっと寄り添い、とくに何か言葉をかけられなくてもいい。
ただ、そばにいて、自分のつらさをわかろうとしてくれる。 何度も、何百回も、何千回も親に話を聞いてもらって、自分の気持ちを言葉にしようとして、やっと伝わり、嬉しくなる。 |
こういう感覚です。
逆に親にあまり話を聞いてもらえなかったり、『親の興味の範囲にある話』しか聞いてもらえなかったり、自分の性格や思考を決めつけて成長して変化しつづけている自分を知ろうともしないし気づいてもらえない。
親の思うスケジュール感で過ごすことや、親の価値観の範囲で成長するほうが優先され、時に抑えつけられ、批判される。
自分らしさは何かということを考える前に、親が望む自分であらねばならない感覚を植え付けられ、自立を急がされ、「精神的に依存してくるな。一人で乗り越えていけ」と言われているような感覚に陥る。
「お母さん、今日ね、こんなことがあったんだ」という話に対し、「それは悲しかったね」と一緒に傷ついたり、悲しい気持ちをわかろうとせず、「それはあなたがわるい」と言われたり、表面的には共感しているように見えるけれども「とりあえずオウム返ししとけ」的な反応だと、子どもはすぐに見抜きます。
このように、親と感情の共有がないと、人は孤立することに恐怖を感じます。
まとめ:「頑張らないと認めてもらえない」という呪縛
感情の共有の仕方をしらない。そもそも感情をだれかと共有するという概念すらない。
社会の規範は自分でまなび理解した。親にちゃんと教わった記憶がない。
親の自分にむけた注意や怒られたことは、『親がこまること』『親が許せないこと』『親の虫の居所がわるい』など、社会的にであるとか、生きていくうえで絶対にゆずれない・教えたいことなのではなく、たんに感情をぶつけたかったり、自分を思い通りにしたいからであった。
だから、自分で社会の規範を学ぶ必要があった。
そしてそれを自分なりに守ろうと必死な毎日。
親と感情の共有が出来ていれば、自分の気持ちをわかってくれる人がいるという安心と、話をきいてもらってスッキリした気持ちで自分の時間を楽しめたりするものの、そのような経験がなかった子どもは、大人になって終わりのない無期限のがんばりをせざるを得なくなることがあります。
誰にも感情の共有の仕方もわからないし、感情を誰かと共有する概念すらないから、とにかく社会に適応しよう。頑張らなければ。
認められなければ。そういう焦りと不安でいっぱいになります。
親に話を聞いてもらった、わかってもらえた、向き合ってもらえたと思えなかった子どもは、大人になっても彷徨い続けてしまう。
就職しても、結婚しても、親になっても、ずっとずっと自分に自信をもてないまま、日々を過ごすことになってしまう。
見た目は大人なのに、中身は子どものままで。
…そういう家庭を、親御さんを、わたしはたくさん見てきました。
今回は、経験のある親御さんからすればちょっとしんどい内容だったかもしれません。
しかし、実はこういう感覚を持ち悩んでいる方は珍しくなく、あなただけではないということを知っていただけると嬉しいです。
それでは、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。
また次回のブログにてお会いしましょう 🙂
まいどん先生(公認心理師)
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇Instagramはこちら