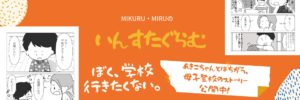『自立を目指す』の落とし穴
ブログをお読みいただきありがとうございます! 🙂
今回は、自立をテーマに、私の過去の経験もふまえて解説をしてみたいと思います。
なんとなく周りが自分に対してどう思っているかがわかっていると…
私は子どものころ、周りの子よりも大きいがたいをしていて、年長の時は親戚から「いま、小学生何年生?」と間違われるほどでした。
そのせいもあってか、幼稚園の先生も、周りの大人も、私を周りの子よりも実際の年齢よりも上の子を扱っているような関わりだったことをよく覚えています。
周りの子は皆、幼稚園の先生から「○○ちゃん(下の名前)」とよばれていたのに、私だけ「○○さん(苗字)」でよばれたり、『困り感のなさそうな子』『しっかりした子』として扱われました。
そのため、幼稚園児ならではの言い争いがあっても、自分が不利になってしまうようなこともしばしば。
その頃から、私自身しっかりした子であらねばならないと幼いながらにも感じていました。
自分でも「そうあらねばならない」と感じていて、かつ周りも自分を「自立させよう」とする状況。
年長なのに、まるで小2くらいのお姉さんのような振る舞いを求められているような感じです。
いま思えばずっと背伸びをし続ける環境であり、心が追いついていなかったなと感じています。
子どもらしく振舞いたい
本当は自分も周りの子のように扱ってもらいたかったし、たくさん甘えたい気持ちでいっぱいでした。
でも、できなかったんです。
「もうそんな時期はすぎたはずなのに、どうしちゃったの?」
…と言われるような気がして。人によっては、甘えを嫌がられたり鬱陶しがられる気がして。
「周りの思う自分」ではない振る舞いをしてしまうと、嫌われたり、受け入れてもらえないような不安が幼いながらにもあったんですね。
ペアレンツキャンプにおいても、よく『年齢相応の自立』という言葉が使われますが、これは実年齢よりも精神・行動面が幼い子を成長させましょうという意味合いがふくまれますが、実年齢を上回ってより成長させよう・自立させようという意味ではありません。
このあたりはよく誤解されがちなんですけど、私が体験したことのように、心は実年齢であるにも関わらず、行動面では1、2学年上の子として扱われ、「自立しなさい。何でも自分でできなきゃだめでしょ」と言われたり、その年齢ならばできなくて当然なはずなのに、できないことに対して親が腹を立てたり不安になって、できていないところばかり指摘されてしまうというのは、子どもにとってはつらいことともいえます。
加えて、『この年齢の子はこれくらいはできておいたほうがよい』というのはあくまでも目安でしかありません。
まとめ
たとえ発達がのんびりさんであっても、よく見ると本人なりにこころ・からだ・行動が成長しています。
就学後は乳幼児検診みたいに発達度合いをはかるようなこともありませんし、よけいにうちの子大丈夫?と不安になると思います。
ですが、よそのお子さんと比べて評価する相対的なものの見方ではなく、わが子が過去とくらべてどうかと評価する絶対的なものの見方をされることを私はおすすめしたいです。
いまは苦手なことがあっても、5年、10年後も苦手なままとは限りません。
逆上がりができないまま大人になった私なので、たしかにそのように子どものうちにできるように訓練しなかったことでそのまま大人になってもできないことがあるかもしれません。
でも、それでも生きていく上では困りごとはありません。ほかにも苦手なことはたくさんありますが、結論としては、自分という個性をどのように生かしながら他者と関わり、自分を大切にしながらも社会で活躍していくかではないかと私は思います。
焦って自立させようとして、甘えたい時期を満喫させられないと、大人になってもどこかずっとさみしいような、心に穴があきっぱなしのような、そういう感覚を持たせてしまうかもしれません。
それでは、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。
また次回のブログにてお会いしましょう 🙂
まいどん先生(公認心理師)
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇Instagramはこちら
👇不登校復学支援をご検討中のかたはよければこちらをご覧ください👇