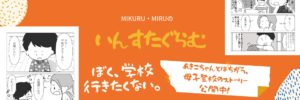母子登校中の子どもたちが見る世界
どうしてひとりで学校にいけないんだろう

本人すらわからないということがほとんどです。
どうしてかわからないけれど、学校がこわい。
みんなは時間までに学校にたどり着き、上靴に履き替え、教室に流れていく。
まるで背中にネジがついているみたいに、全自動で勝手に身体が動いているみたいに、当たり前に教室に吸い込まれていく。
でも、自分の背中にはネジがない。
自分だけが立ち止まってしまって、自分だけがみんなと同じように当たり前に動けなくて、みんなよりも何か怖い暗いものが心の中にあって。
どうしてなのかはわからない。

と聞かれても、自分でもわからない。
だから、思いつく限りのいやなことや不安なことを言葉にしてみる。
授業がいや。体育がいや。中休みがいや。給食がいや。掃除がいや。親友と呼べるお友達がいない。先生がこわい・・・
でも、先生や親が見るかぎり、いじめにあってるわけでもないし、授業にもなんとかついていけているし、給食もたべられている。
「目立って困りごとがありそうにないのに、どうしてこの子はひとりで学校に行けないんだろう」と、周りはひとりで行けなくなった理由やきっかけを探そうとします。
低学年の子にとって、こころのモヤモヤを言語化するのは難しい
たとえ表面的にはそこまで深刻さや困り感が見えなかったとしても、クラスメートにいじめられていなかったとしても、本人にしかわからない怖さがあったりします。
勉強も、先生のお話が2倍速くらい早く感じてなにを言ってるかわからないとか、板書が早すぎたり、手先が不器用で体育前に着替えるのが難しかったり、給食を時間内に食べなきゃというプレッシャーがあったり、そういう本人なりの大変さが、本人もうまく言葉にできなくて、不安をふくらませているかもしれません。
自分はまわりとは違うんだ。みんなみたいに当たり前のように教室に吸い込まれ、話をし、ふざけあい、授業を受けられない。

どうして自分はできないんだろう。
まるで自分は宇宙人かのように、別世界の人間のように感じてしまう。
できない自分がどんどん嫌になって、信じられなくなって、まわりの優しさをも拒否してしまって、孤独になりたがり、自分を守ろうとして、自分を守るために殻にとじこもろうとしてしまう子もいます。
モヤモヤを言語化できていない段階で結果を急がれるとよけいに怖さが増してしまう
そう考えますと、母子登校で悩む子たちの一番の困りごとは、
どうして学校にひとりでいけないのかと理由を問われることや、きっかけとなった不安ごとだけを解消しようと周りの大人が環境を整えたり提案してくることなど、
「はやく学校という型にはまってあなたも当たり前のように毎日を過ごしなさい」
と言われているような、そういった、自分のみている世界をわかろうと・知ろうとしてくれる存在がいないということなのかもしれません。
ママは、先生は味方だよ。
そんなふうに言われて、たしかに助けてもらっているのだけれど、それなのに、時々本当に味方?と疑いたくなってしまう。

どうして味方なのに、早くひとりで行けるようになりなさいとか、
もう何年生なのに恥ずかしいとか、いやな言葉を言うのだろう。
自分だってこうなりたくてわざとやってるんじゃない。自分だってわからないのに。
今日も学校がこわい。
今日も不安でいっぱい。
…と、こんなふうに、余計に不安が増してしまっている子も多くみかけます。
まとめ
これはあくまでも一例ですし、すべての母子登校中のお子さんがこうだという話ではありません。
もちろん親の子への関わりが幼すぎるがゆえに学校環境に適応できていない場合もありますし(拙著のあきこちゃんのパターンのように)、それ以外のパターンもあり得ます。
👇これについては、詳しくは過去のブログで解説しているのでそちらをご覧ください👇
「親も子の話を聞いてきて、不安な気持ちや怖さに寄り添ってきていますし、この子は言語化出来ているとおもうのですが…でも、どう寄り添えばいいかわかりません」と仰る方も多いです。
しかし、実際にカウンセリングを受けていただくと、まだまだ言語化できていないことがあったり、異なる視点・角度からお子さんを見ることができるという発見があったりもします。
誰もがそうですが、人のことは良く見えて、自分のことはなかなか客観的には見れないものです。
(私も自分のこととなれば主観が入りすぎてしまって事実とはことなる捉え方をしているなと感じることが多いです)
客観的に家庭の状況を見ていくということは、母子登校を乗り越えるということだけではなく、お子さんへの理解の深まりにもつながっていくので、今回のブログを読んで「もしかしたらうちの子はこういうことを考えていたのかもしれないな…」と感じられた方は、いつもとは少し違った角度からお子さんの様子を観察されてみるとよいかも知れません。
それでは、今回はこのへんで終わりたいとおもいます。
また次回のブログにてお会いしましょう 🙂
まいどん先生(公認心理師)
👇応援よろしくお願いします!!
![]()
にほんブログ村
👇Instagramはこちら